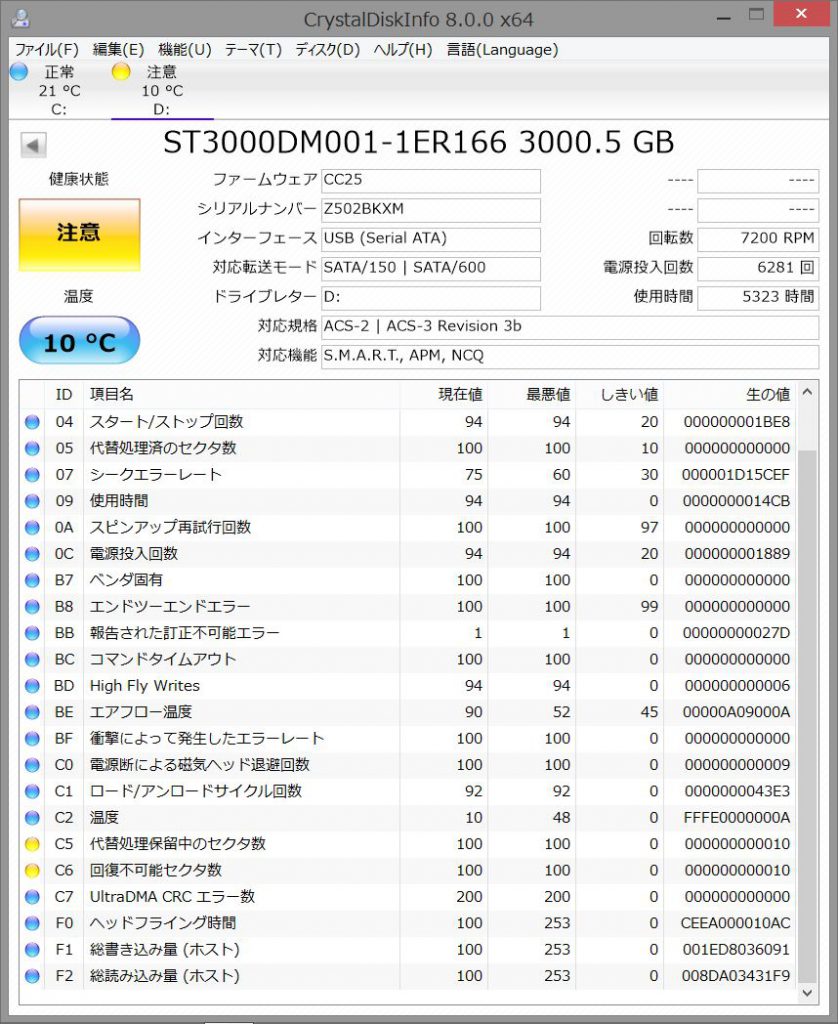今回は、HDDを交換するようになるちょっと前から、気になる挙動がありました。
録画用PCにだったんで、動画ファイルを他のPCにコピーしたりするコトが多いんですが、その時に急激に転送速度が落ちることがときどき起き始めました。
ギガビットイーサネットなので、Windows上の表示では110MB/sほど出るんですが、それが1/3ぐらいになるときがあってしばらくすると元に戻る。
それがある時、1/10ぐらいにまで落ち込んで、なかなか戻らなくなったのでCrystalDiskInfoでS.M.A.R.T情報を確認したところ以下のような感じ。
詳細までは読み解け無いんですが、ようは不良セクタが多く発生してきてるので対処が必要…というコト。
だましだましやればまた使えるのかもしれないですが、それで大事なファイルを失ったり、余計に時間を使ったり、不要な心配をしたりというコトにリソースを割きたくないですから。
すっぱり交換です。
HDDの使い方を見直し
今まで録画PC(兼ファイルサーバー)として運用してた、今回故障したHDDを古い2TBHDDに変更して録画専用に交換。
古いHDDですが、万が一HDDが突如故障しても、その日の録画ファイルを失うだけで被害を抑えられます。
その上で、新しく購入した4TBHDDを、バックアップ用の外付けHDDとして運用することにしました。
--- ads by google ---
--- end of ads ---
いままでファイルサーバーに入れてたファイルはこちらに移動。
なるべく稼働時間を抑えて長持ちさせるような運用でいきます。
ストレージの運用ポリシーの変更
PCに大容量HDDを常時内蔵するんじゃなくて、必要なファイルを、必要な時に外付けHDDを接続してアクセスする方向性へとポリシーを見直しです。
USB3.0で接続すれば、それほどファイルコピーにストレスは無いですから。
日常的に頻繁に利用するファイルは、ネットストレージで同期させますが、それから外れたファイルへのアクセスは非常に稀です。
そのためにHDDを内蔵させて常時稼働させるのは、HDDの寿命を考えても少々勿体無い。
HDDの単価はたいしたコトないですが、トラブル発生時に生じるファイル喪失のリスクや、トラブルリカバリーに必要な時間が勿体ないですので。
それは最小限にしたい。
SSDはシステム用。
HDDはデータ保存用。
そのデータ保存も、常時使うものをSSD&ネットストレージで運用して、使用頻度の低いデータは外付けHDDとして運用。
SSDの大容量化も進んでますし、NASの普及もありますし、いろいろと変えてかないといけない時期のようです。